8月8日に中小路小学校で学校運営協議会(以下、CSと略)をテーマにした教職員向けの校内研修会「地域で育てる子供たち~学校運営協議会とPTAのこれから」と題し研修会の講師を務めました。
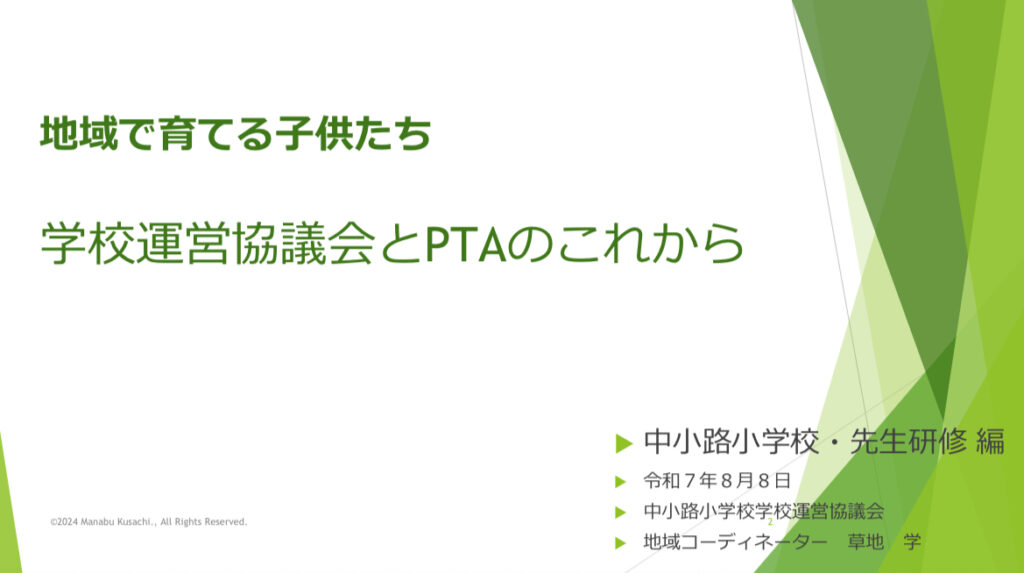
今回の研修実施にあたっては、中小路小学校の斉藤校長先生、町田教頭先生と協議を重ね開催する運びになりました、ありがとうございました。 研修会の開催意図ですが、まだスタートしたばかりのCSをこれからの時代を担う若い先生に理解して頂き、CSの種まきが最大の目的です。
まず最初にお聞きしたのは「CSを知っていますか?」というシンプルな質問です。
もちろん名前が分かるのではなくどのような仕組みかといことです。
結果として大半の方の手は上がりませんでした。
初めての試みですから手が上げやすいムードでは無かったかな….。
次にはPTAがなぜ誕生したのか、どのような組織で活動しているのかを説明。
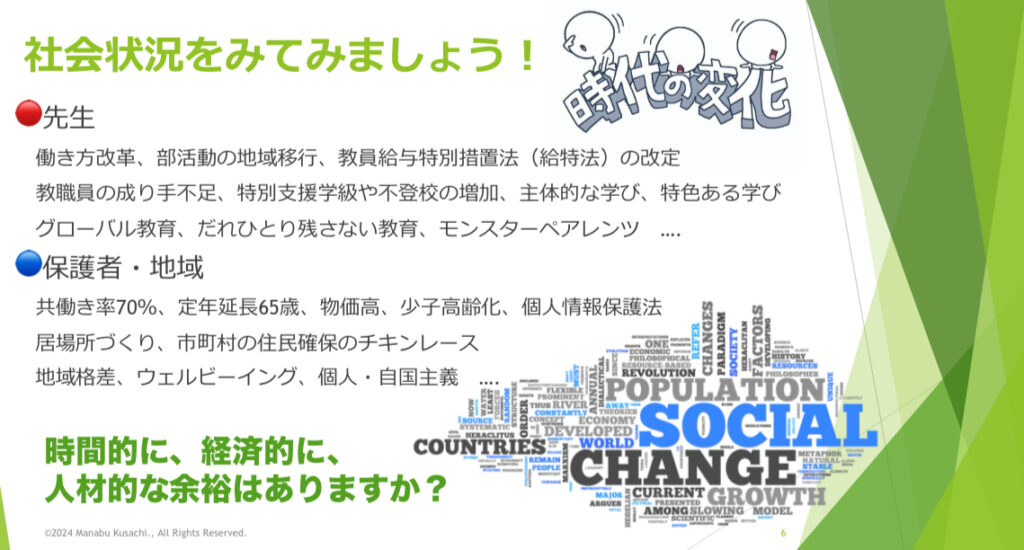
しかし、CS=学校評議会やPTAなどと区別できないところもありますので、先生、PTAやコミュニティの今の状況から説明しました。
先生の状況は働き方改革・部活動の地域移行…etc 。
保護者やコミュニティの状況でも共働きが7割を超え、定年の65歳延長などこちらも…etc。
コロナ禍の後の時代は、様々な社会変化が山積みなんです。
そんな時代に時間的に・経済的に人材的な余裕はありません、個々を認識することが大事です。
CSは先生のサポートする仕組みですし、先生も独りではなくサポーターを募っていいのです。
まずはここを分かっていただくと、じゃあどうすればいいのかにつながるはずです。
小学校であれば「ミシン操作・昔遊び」を子供たちに教えることは難しい、じゃあ地域の人に協力を仰ごう。
中学校は「職場体験」の受け入れ先の調整などが地域の出番です。
分かっているけど簡単にいかないのがPTAやコミュニティなんですよ。
なぜか!?
教職員の先生は、管理職(校長・教頭)は2~3年で、教諭の場合は長くても7年程度で人事異動になるんですよ。
しかも、隣の学校ではなく違う市町村への異動も多いのです。
これでは新た赴任先でゼロベースのPTAやコミュニティのネットワーク作りは非常にハードルが高い。
もちろん先生も人づきあいが得意・不得意な方がいますから…。
そのためにCSがあり、私みたいな地域コーディネーターがつなぎ手として必要なんです。
今回の研修ではCSが近くになるための第一歩なことを宣誓にお伝えしました!
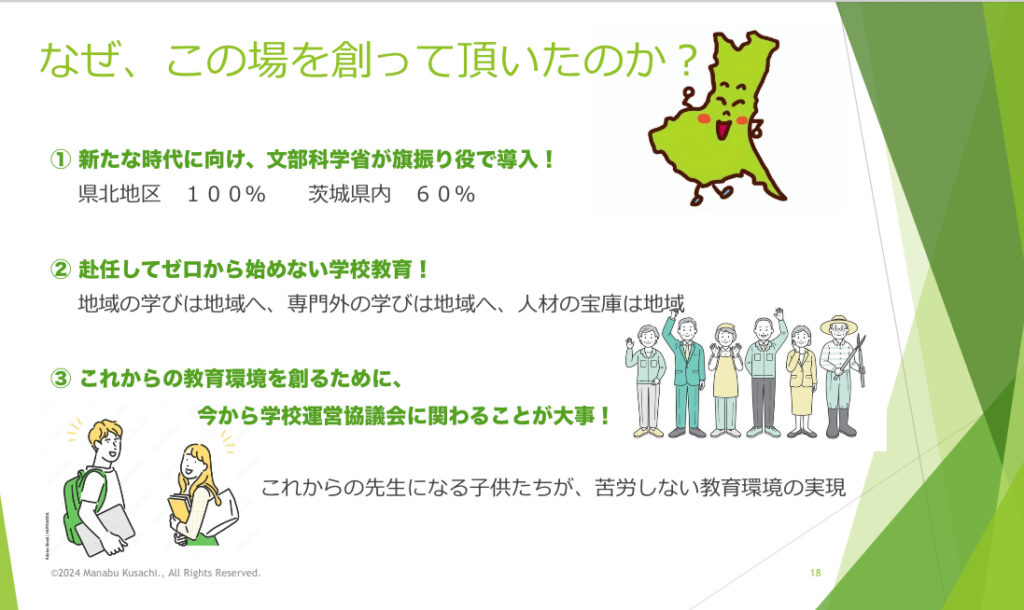
次は先生と地域・保護者で「熟議」してみたいですね。
やっと今回の先生向けの研修、7月のCS委員向けの研修をやりましたので。
早く社会教育士の資格を取らねば!
このようなCSのはじめの一歩、PTAをもっと教えてという方がいればお伺いしますのでお気軽にお声がけください。
まずは知ることから始めよう~☆


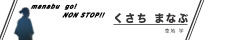




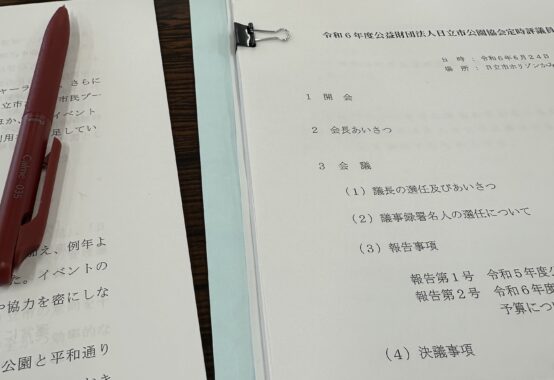
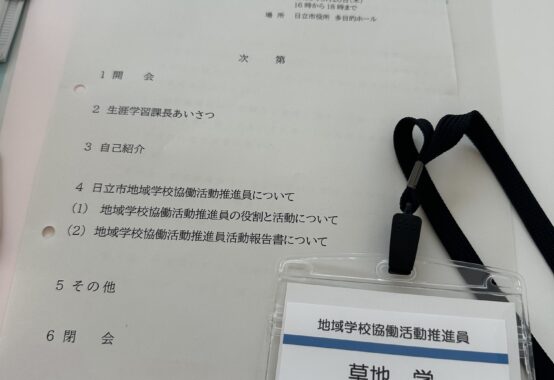
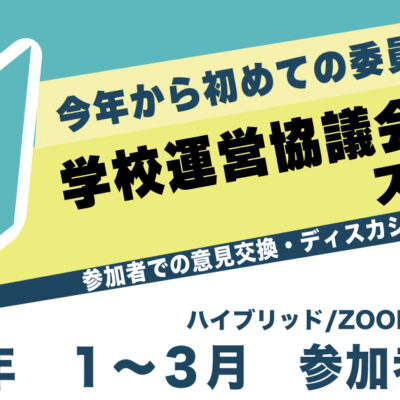




この記事へのコメントはありません。